どうも!
今日は、ここ数年で大きな進展を見せているiPS細胞研究についてご紹介します。
iPS細胞とは?
**iPS細胞(人工多能性幹細胞)**は、2006年にマウスで初めて作製されました。
これは、「人工的に作り出された、どんな細胞にも変化できる細胞」のことです。
本来、人間の受精卵は細胞分裂を繰り返し、成長しながら特定の機能を持つ細胞(分化細胞)に変化していきます。受精卵はあらゆる細胞に変化できる能力を持っていますが、一度分化してしまうと、他の細胞に変わることはできません。
ここで重要なのは、受精卵も分化細胞も同じ遺伝子を持っているということです。つまり、「同じ遺伝子を持っていても、その発現や抑制により分化した場合、元の細胞に戻ることができない」ということです。
しかし、iPS細胞は、分化細胞に特定の遺伝子を導入し、細胞を初期化することで「どんな細胞にもなれる性質」を取り戻させた細胞です。
ES細胞との違いと課題
従来からES細胞を使った研究は進められていましたが、ES細胞は受精卵由来のため倫理的な問題がつきまといました。
一方、iPS細胞は倫理的ハードルが低く、より広範な研究・治療応用が期待されています。
ただし、懸念されるのは「がん化のリスク」です。細胞は癌化することがあります。IPS細胞のように人工的に初期化し、分化させた細胞ではよりリスクが高いと判断するのは当然のことと思います。
しかし、現在までの治験の経過観察では深刻な問題は報告されていません。リスクはないわけではないですが、病気に対する有効性と現在の安全性の確認経過を見ると積極的に研究を進めてほしいですね。
iPS細胞研究の進展と実用化への道
iPS細胞を使った研究は多岐に渡ります。
- 特定の細胞への分化誘導
- 3次元臓器作成
- 治療への応用技術の開発
これらは非常に高度な技術ですが、発見から約20年が経ち、今では次のような成果が出ています。
- 網膜シートの作成と移植・先進医療承認
- 心筋シートの作成
- パーキンソン病患者へのドーパミン産生細胞の移植
- 糖尿病患者へのインスリン産生細胞の移植治験
- 脊髄損傷患者への治療応用
- 慢性腎障害に対する治験準備
特に眼科分野では、先進医療の許可も下り、今後の成果に大きな期待が寄せられています。
パーキンソン病治療での朗報
最近注目を集めたのは、京都大学による**「iPS細胞を用いたパーキンソン病治療治験」**です。
この治験では7人(50~69歳)のパーキンソン病患者にiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞を脳内の両側被殻に移植しています。結果、健康への悪影響は見られませんでした。さらに、機能評価を行った6人中4人に症状改善が見られました。若くて、症状の軽い患者さんには効果が高そうだということもわかってきたそうです。
パーキンソン病とは?
パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質**「ドーパミン」**の不足によって発症します。ドーパミンは体の動きをスムーズにする役割があり、不足すると以下のような運動障害が生じます。
- 安静時でも震え(振戦)が出る
- 歩行が小刻みになる
- 方向転換が困難になる
- 動き始めが遅くなる
- 転びやすくなる
今後は「どの患者さんに、どれくらいの細胞を移植すれば最適か」『有効率の評価』という課題に取り組んでいくフェーズに入るでしょう。
早期の実用化に期待が高まります!
将来的には、自分の細胞から作成された自家IPS細胞(my IPS細胞)で拒絶反応のリスクの低い治療も期待されますね!
では、また!
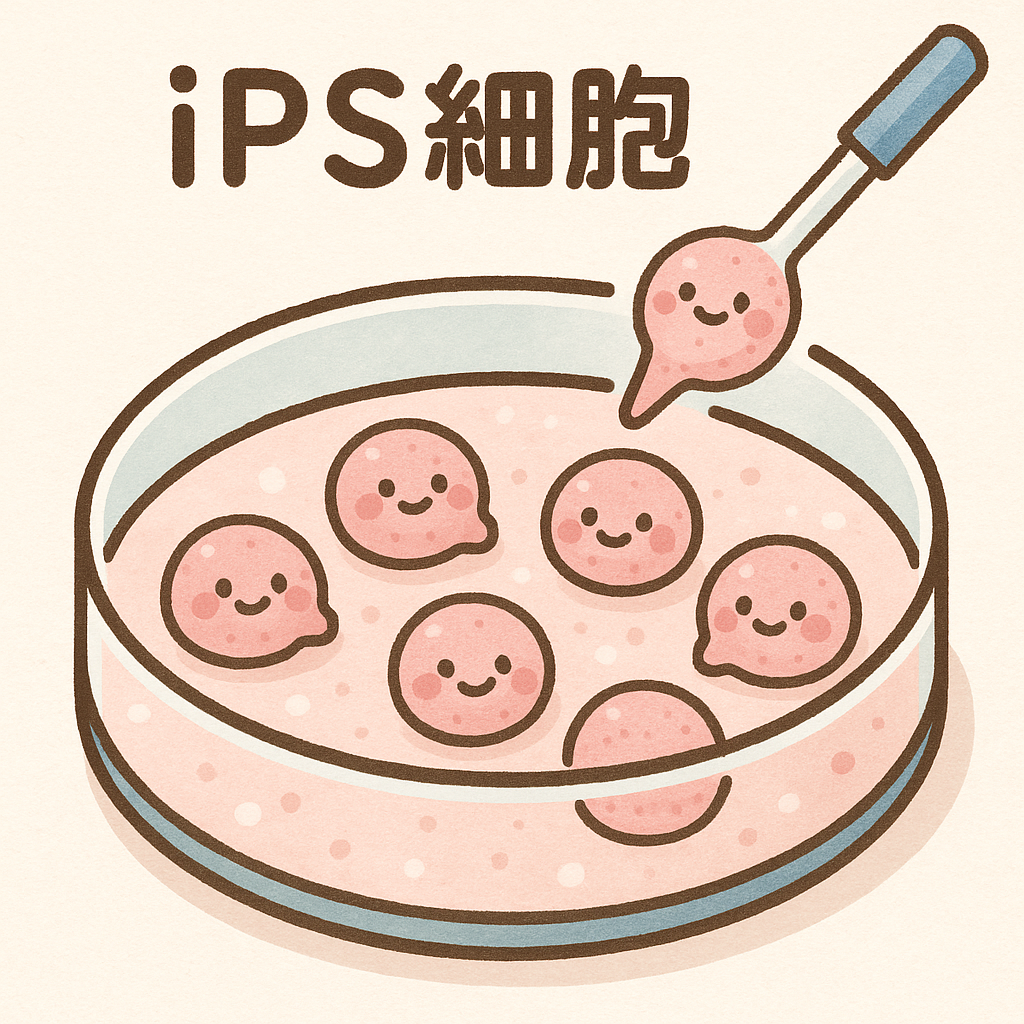


コメント